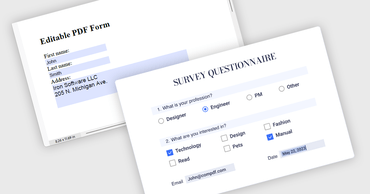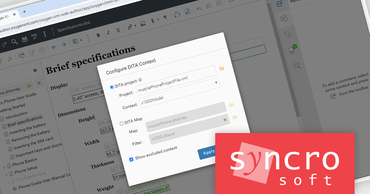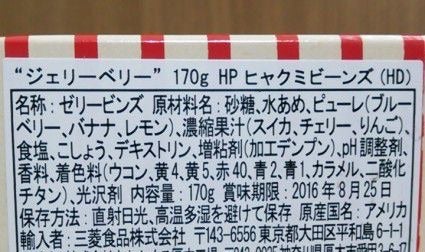入江悠は、戦っている人だと思う。自分が本当に作りたいものを追求して自主制作で「SRサイタマノラッパー」三部作を作ったこともそうだし、映画の主人公たちも皆もがき戦っている。因習にとらわれず、実績に安住しないスタイルを貫き続ける彼はどんな死生観を持っているのか。

病弱だったから早く死ぬと思っていた
入江 今は60くらいがいいなあ、という感じなんですけどね。もっと若いときは「50くらいで死ぬんじゃないか」と思ってたんですけど、今はちょっと延びて「60くらいでもいいじゃないか」っていう。
入江 太く短くっていうか……。なんか、「老いて介護されるとか嫌だな」という感じがあったので。
入江 そうですね。自分の仕事が映画だから、けっこう体力勝負な部分があって。80超えてやってる人もたまにいますけど、「あんなにできるわけがない!」って思ってるので(笑)。
入江 そういう人もいるんですけど、それは本当に一握り、五本の指に入るくらいの人しかやってないと思うんですよ。それ以外の人は大学の先生とかになるんでしょうけど……なんか「退いた感」が嫌で。そこで未練持ってるのも嫌だなあ、っていう感じがするんですよね。
入江 家系的にはそうかもしれないですね。ただ、自分自身は子どもの頃、病弱だったんですよ。だから死生観という意味では、「早めに死ぬんじゃないか?」みたいに思ってましたね。
入江 小学校の時は、学年で五本の指に入るくらい弱かった。風邪とかですぐ休むし、喘息もあったし。だから、その頃からなんとなく「自分は弱いんだ」っていうのが刷り込まれたんですよ。
入江 何ですかね……身内で爺さんが死んだのが最初ですかね。
入江 きっかけはわからないんですけど、「死」というものがあるとわかって、眠れなくなったり夢に見たりしていたのは、小学校低学年くらいの頃からありましたね。「宇宙が歪んでいく」みたいな夢を見た記憶があります。何の影響でそういう夢を見たのかはわからないんですけど、そのちょっと後くらいに手塚治虫の『ブッダ』を読んだときにも同じようなことはありましたね。
入江 小学校低学年だったと思うんですけど。
入江 『ブッダ』を読んで、(死について)「ああ、これはひとごとじゃないな」と感じた記憶がありますね。
身近な人より、ちょっと接点がある人の死のほうがショック
入江 子どもの頃はやっぱり体が弱かったんで、「こんなに苦しいんだったら死んでしまったほうがいいんじゃないか」っていうのは思っていましたね。
入江 ええ。中学校とか、高校くらいまでそれはあったかもしれないですね。喘息がひどくて、息ができないくらいになると、「こんなに苦しいんだったら……」みたいな。
入江 変わらないですね。「基本的にいつ死ぬかわからない」というのは、もう刷り込まれてしまっていることなので。最近、テレビの仕事もいただくようになったんですけど、「撮り終わって死んだらこれが遺作になるけど、いいんだろうか?」っていうのを、いまだに思いますね。「いつ死ぬかわからない」っていうのは、子どものとき本当に思っていたことなんですよ。そんなに死が身近にあったわけじゃないんですけど、中学一年の時に同じクラスだった、自分よりも病弱で、ほとんど学校来ない奴がいて……僕らが高校生になったばっかりのときに、そいつが死んだんですよ。みんなで葬式に行ったんですけど、「確かに学校休みがちだったけど、同じクラスだった奴がこんなにあっさり死ぬか」と思って。他の同級生は、みんなバラバラの高校に行って、久しぶりにその葬式で再会したから、楽しみなわけですよ(笑)。
入江 話したことは何回かある、っていうくらいの。あの唐突な死に方っていうのは……15くらいで死んじゃってるわけですよね。なんか、虚しさみたいなのは感じましたよね。
入江 あんまりないんですよね。親族の死っていうのがあんまりないし、親友が死んだっていうのもなくて。そういうのより、ちょっと接点があった人があっさり死ぬほうがショックがあって。
入江 高三のときに後ろの席にいた奴が、大学受験の下見に行って、車ではねられて死んだんですよ。「ああ、後ろにいたあいつ、死んだんだ……」っていう。親族とかの死よりも、そっちのほうが何かこう……。
入江 そうですね。虚無感みたいなの、すごい感じますね。
入江 ああ、それは生じるんじゃないですかね。高校生のときは男子校だったんですけど、そこから比べたら完全に減衰してるじゃないですか(笑)。
入江 いやいや、あんときに比べたら、たぶんもう半分以下になってると思うんですよ。あの頃って欲望だらけだったと思うんですけど、そういう欲望が少しずつなくなっていって……。
入江 知識欲とか、権力欲とか。わりと減ってきた感じはするんですよね。それが……もうゼロになってしまったときには、「死にたいな」と思いますけどね。
入江 けっこうそうなんですよ。子どものときから、そこはあきらめてたので。さっき言った、親族よりも「ちょっと近いくらいの人」の死のほうに心を動かされるというか。「物質としての死」みたいなのがあるじゃないですか。あっさり切られる感覚っていうか。
入江 子どものときから、死ってそういうものだと思っていたので。
死後、魂が続いていくほうが残酷だと思う
入江 どっちかっていうとそっちのほうが幸せなんじゃないか、って思ってるんですよ。むしろフェードアウトしていくほうが残酷なんじゃないか、っていう。
入江 あれが嫌なんですよね。一番理想なのは、「撮影終わって、『疲れたな』つって寝たらそのまま起きなかった」みたいな終わり方。
入江 そうですね(笑)。それが一番いいですけど、たぶんそうならないことが怖いですよね。
入江 ないですないです。「自分の死に際を看取られるなんて絶対に嫌だ」っていう感覚はありますね。人知れず死んで終わりたい(笑)。
入江 学生時代はそういうのに興味があっていろいろ読み漁ったんですけど、今としては、やっぱり何もなくなるというか、「完全な無」みたいな感覚のほうが強いですけどね。
入江 そうですね。むしろ、「その魂が続くほうが残酷じゃないか」っていう気がするんですよ。今、ダンテの『神曲』を読んでるんですけど、あれは地獄めぐりの話じゃないですか。あれとかもう「なんて残酷なんだろう!」って思う。プツッ!といったほうが気持ちがいいというか。
入江 どうなんだろう……すごい怖いと思うんですよね。昔はよくそういうこと考えてて、結論が出ないまま今日に至ってるんですけど。……たぶん、やりたかったけどやっていなかったことをやると思うんですけどね、最初は。
入江 そういうのもどこかの時点で虚しさが来ると思うんですよ。……だからそういうのは恐ろしいですよ。そこまで自分が告知されたら、っていうのを考えると、めちゃくちゃビビります。

睡眠時間が長いから、生きてる時間が人より短いのかも
入江 やっぱり20代途中くらいから考えなくなりましたね。
入江 たぶんそうだと思うんですよ。でも、それでごまかしてるだけだと思うんですよね。「お金を稼ぐ」とか、「何を食う」とか、そういうことでごまかしてるんだと思うんですよ。
入江 そうですね。暇だったから、そういうのばっかり考えてたんでしょうね。
入江 いや、たぶん一緒だと思います。その恐怖みたいなものを、日々のことで紛らわしているかどうかの違いだけで。しかも、いま話していて思い出したんですけど、寝るのがすごい好きなんですよね。8時間くらい寝ないとダメなんですよ。4〜5時間しか寝なくても平気みたいな人もいますけど。
入江 いますね。そういう人たちよりは、5時間くらい多いわけですよ。60年生きたとしても、トータルですごい寝てるので、人よりも生きてる時間が短いかもしれない(笑)。だから、生きることを充実させるというか、満喫するっていう意識がすごい薄いんですよ。あらかじめ睡眠時間ですごい削られてるんで。
入江 やることなければ12時間は普通に寝られますね。大学時代は本当に引きこもってて、「15時間寝て、起きて、TSUTAYA行って、BOOKOFF行って、家帰る」みたいなトライアングルでずっと生活してたので。それがもう日常だったんですよ。家庭教師のバイトをちょっとやってたんですけど、授業が7時スタートなんですね。あるとき起きたら6時50分で、「ヤバい!これは遅刻だ!」って思って、慌てて「今日遅刻します!」って電話したんですよ。で、電話を切ったら、朝だった(笑)。
入江 朝の6時50分に「遅刻する!」っていう電話を生徒にしてしまい、そのときに、「ああ、終わったな……」と思って。それくらい、逆転した生活をしてましたね。だから、アメリカとかの、MBA的な考えってあるじゃないですか。効率良く、合理的に、っていう。そういうのから一番遠いかもしれないですね。「自分は人生のリソース的なものが人より少ない」っていうところからスタートしてるんですよ。だから、無駄なこと、やりたくないことに時間を使いたくないんです。
入江 あの時は本当に、「これでダメだったらやめよう」って真面目に考えてたんで。でも、自殺はできないんですよね。生きなきゃいけない、と。寿命も続くだろうから。でも、映画と人生が切り離されることが、すごい恐ろしかったんですよ。
入江 それだったら本当に思い切って違うことをやんないといけないでしょうね。それこそ、中国に行って、大陸浪人のように変なモノを売りまくるとか(笑)。それくらいのことをしないと生きていけないって思ってましたね。じゃないと、本当に無気力になるというか、生きている意味がなくなるんで。
入江 やっぱりこれしかないんですよね。接客もできないし、バイトも嫌だったんですよ。フリーでやってたけど食えなくて、一年間だけ会社勤めをやってた時期があったんですけど、やっぱり嫌になって。「明日死ぬかもしれない」って思うと、「貧乏でも好きなことやろう」と思って辞めちゃったりして。そういう意味では、自分ができることって本当に少ないんですよ。仕事として映画ってのを設定したから、生きていられるというか。
入江 そうですね。それ以外のことはなるべくやりたくないです。『サイタマノラッパー』のメンバーは、大学の後輩だったり同級生だったりするんですけど、僕は本当に彼らとプライベートで会わないんですよ。友だちと飲みに行こうとか、まったくない。撮影が終わって、映画が完成して、それで終わりというか。
入江 そう。そこに対して、ないんですよ。哲学者の中島義道の『人生を〈半分〉降りる』っていう本があるんですけど、大学のときはそれに近い感覚でしたね。自分は社交性もないし、生存能力もないし、寝過ぎてるし(笑)。そこでちょっと「降りた」というか、楽になった感じはあったんですよね。
パニック映画における死の描き方
入江 今の自分から考えると、60くらいで『宇宙戦争』を撮って死ねればいいですね。過程は何でもいい、途中はどうでもいい。最近亡くなった新藤兼人さんのように、歳を重ねた人にしか撮れない映画もあると思うんですけど、それよりは、そこのピークでパタッと力尽きたいな、というのがあります。
入江 言ったり言わなかったりですね。『宇宙戦争』というより、『宇宙戦争』的なパニック映画ですね。いまだにパニック映画は上映されてたら見に行きますからね。パニック映画って、死が唐突に訪れるじゃないですか。そこに惹かれるんですよ。『アルマゲドン』と同時期にやってたせいで影が薄くなっちゃった、『ディープインパクト』っていう映画があるんですけど、それがすごい好きなんです。あれも津波が来て、逃げられる人と逃げられない人がいて、車で逃げた人はみんな渋滞でダメなんですよ。で、主人公はバイクでススッ逃げられる、っていう。それを見て浪人生時代にバイク買いましたからね(笑)!
入江 (避難するための)船に乗るときに、橋が上がるじゃないですか。で、ここに引っかかって落ちちゃう人がいますよね。あれが描けてないと、僕はパニック映画だと思わないんですよね。それを描けてたら、そこだけでもう好きになるというか。『宇宙戦争』は、もうそういうのだらけじゃないですか(笑)。「橋に引っかかって落ちた奴と、運良く船に乗れた奴の違いって何なんだろう」みたいな。あれが死っていうものを思い出させてくれるというか。そこの、何の意味もない、ただ本当にちょっとした違いで生死が分かれるっていうのが、「すごい誠実だな」と思うんですよ。
入江 本当は、自分のサインというか、クレジットがない状態で残るのが理想なんですよね。エンドロールが長々と流れるじゃないですか。あれは要らなくて、もう「END!(ドーン!)」つって終わる。誰が作ったかわからない。そういうのがいいです。
入江 もちろん、「これが自分の今持ってるすべてを注いだ映画だ!」って言うことの心地良さはあるんですけど、死んだあとはもう関係ないというか。その映画が見られ続けたら、それはうれしいですけどね。
入江 それは本当に怖いですよね。たぶん、「誰にも見向きもされない」だったら、留保つきだからごまかせると思うんですよ。「いつかは!」っていうのがあるから。でも、目が見えなくなるのは……けっこう絶望的な気持ちになりますね。ベートーヴェンみたいに、口述で脚本だけをするのか……(笑)。
入江 うん。でも、自分の作ったものは、もう完全に見れないわけですからね。「本当に自分にできることがなくなったときは、死ねたらどれだけ楽か」っていうのはいつも思うんですよね。そこで苦しむのはわかってるから。
入江 撮れるんだったら撮り続けてます。でもそこに残るイメージがあんまりないんですよ、病弱だったんで (笑)。深作欣二さんが好きで、『バトルロワイアル』の一作目が終わったあと、会いに行ったんですよ。「もうそろそろ死ぬかもしれない、いま会わないと死んじゃうぞ」と思って。大学三年くらいのときに会いに行って、大学で講義をしてもらったんですけど、もう積んでるエネルギーが違うんですよ。深作さんはそのとき72歳くらいでしたけど、もう自分よりしゃべるし、すごいですよね。2時間の予定の講義が、4時間になりましたから。
入江 しゃべりっぱなしで。しかも最終的には、大学1年生の女子を上にあげて、「爆弾が近くに落ちたときにどうやって助かるか」っていうレクチャーを(笑)。生への執着がすごいんですよ。
入江 違いますね。あと深作さんも、「学徒動員で働いているときに近くに爆弾が落ちて、それまで一緒にしゃべってた友達がぽっくり死んだ」というのを経験してるので、やっぱり死に対して過剰な思い入れを持ってない。思い切りがいいんですよね。だから、『仁義なき戦い』とかもあっさり死ぬじゃないですか。誰と誰が死亡、みたいにテロップが出てきて。『バトルロワイアル』もそうですよね、あの「生から死に変わる瞬間の早さ」。
入江 ないです。余命何ヶ月みたいなのとはまったく逆の発想だと思います。
死者を代弁することへの抵抗感
入江 ……それで思い出したんですけど、さっき話した「高校生のときに、ぽっくり死んだ奴」っていうのは、(「サイタマノラッパー」に登場する)「タケダ先輩」の元になってて。あんな感じでぽっくり死んだんですよ。「あれっ?生きてたじゃん?」みたいな。で、まあ号泣するほど悲しくもないぞ、っていう。人の死はそういうものだと思ってるから、「死んでいくのを看取る」とか「余命何ヶ月」みたいなのは自分には書けないと思うんですよ。
入江 誰にも聞かれなかったんで言わなかったんですけど。
入江 そうですね。そういう意味では、この前、ジャーナリストの方が死んだじゃないですか。
入江 はい。あれも、その感覚に近いですね。百戦錬磨の人が、ふと見たらもう死んでる、っていう。それが、自分のイメージする死なんですよね。大往生みたいなことより、そっちのほうがリアリティがある。
入江 まあそうですね。基本的にやっぱ、都合よく物語を駆動させるための死って、多いじゃないですか。フィクションの中で。どうしてもそうなりがちなので、できればやりたくないんですけど。
入江 別にそういうのがあってもいいと思うんですけど、でもやっぱりそれは使いやすいんで、ちょっと抵抗がある。まさにスピルバーグの『宇宙戦争』が好きなのは、ふわっと死ぬじゃないですか。粉々になって、パーン!と。あそこまでいったらいいと思うんですけど、死に必要以上の重みを持たせて、物語を転がすのがあんまり好きじゃないんですよね。この前、高橋源一郎さんと対談したんですけど、高橋さんは「死者を代弁することに対して抵抗がある」っていう話をしていて。
入江 例えば、「震災で亡くなった人はきっとこういう気持ちだった」とか。でもそれは死者のことを勝手に代弁しているだけで、本当のところはわからないわけじゃないですか。こっちの人間は。
入江 たぶん全部の場合に、善意が発動してるじゃないですか。そこにすごい傲慢さを感じるんですよ。やっぱり震災の後って、そういうのが生まれやすいというか。第二次世界大戦のあともそういうのがありましたけど。死っていうのは、もっと物質的なことなんじゃないか、って気がします。
入江 そうですね。それが世の中をよくするためだったとしても、何かやっぱりそこに傲慢さを感じるんですよね。
入江 されたくないです。死んだ瞬間に忘れ去られるのがたぶん一番理想かもしれないですね。
入江悠(いりえ・ゆう)
映画監督。1979年、神奈川県横浜市生まれ、埼玉県深谷市育ち。2009年、自主制作の映画『SRサイタマノラッパー』が、ライムスター宇多丸・いとうせいこうなどから絶賛され、ロングランヒット。池袋シネマ・ロサや渋谷ユーロスペースなどで異例の動員記録を残す。10年公開の『SRサイタマノラッパー2~女子ラッパー☆傷だらけのライム~』を経て、12年に『SR サイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者』が公開され、「SR北関東三部作」が完結した。
前田隆弘(まえだ・たかひろ)
広域指定編集業。福岡県出身。ふだんは「TV Bros.」などで書いてます。はじめて死を意識したのは、小学生の時に見たドリフ映画の「いかりや長介が生きたまま火葬される」というシーン。喪失感よりもビジュアルから入ったクチ。
●「何歳まで生きますか?」が本になります
モダンファート連載の死生観インタビュー「何歳まで生きますか?」が、追加取材分を加えて12月21日書籍化! 気になるインタビュイーは掲載順に
二階堂和美/向井秀徳/雨宮まみ/pha/石井光太/真鍋昌平/入江悠/久保ミツロウ/東浩紀/金子平民/渋谷慶一郎/二階堂和美(再インタビュー)
現在、Amazonほかで発売中!
●出版記念トークショーのお知らせ
前田隆弘(まえさん)著「何歳まで生きますか?」出版記念
タナカカツキ著「部屋へ!」とっくに出版されてた記念
トークショー!
原宿LAPNET SHIPで開催中の「PHYSICAL TEMPO HO! HO! HO!」にて、まえさん著「何歳まで生きますか?」出版記念と、タナカカツキ著「部屋へ!」とっくに出版されてた記念を兼ねたトークショーを行います。
日時:12月22日 17:00〜
場所:原宿LAPNET SHIP(東京都渋谷区神宮前1-9-11-1F)
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」5番出口より徒歩2分
JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩5分/p>
詳細はこちらから
http://p-tempo.posterous.com/1222-1830
●「デジオ 何歳まで生きますか?」
著者のまえさん自ら、本についてあれこれ語ります。
http://nansaimade.tumblr.com/